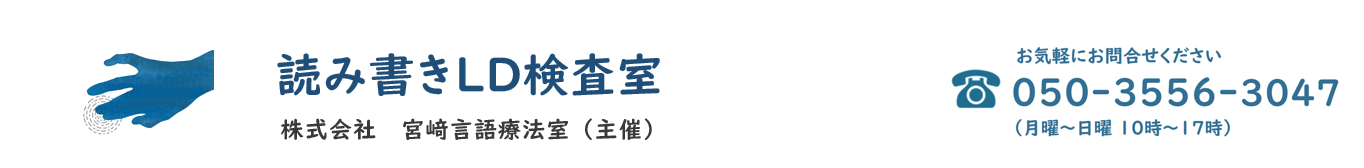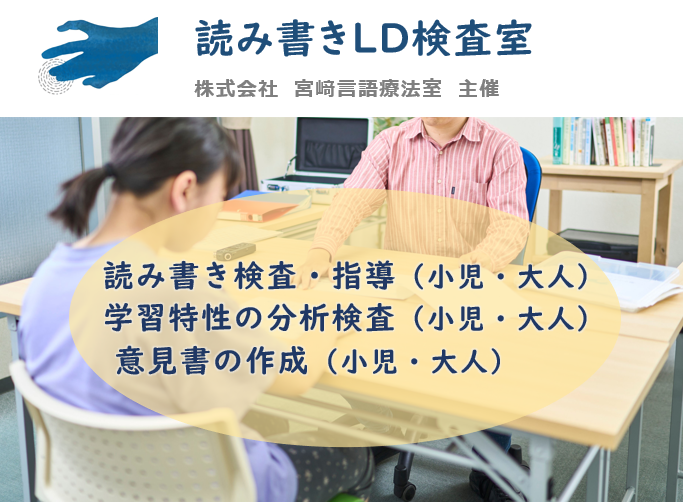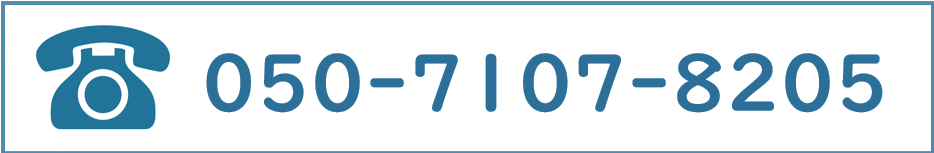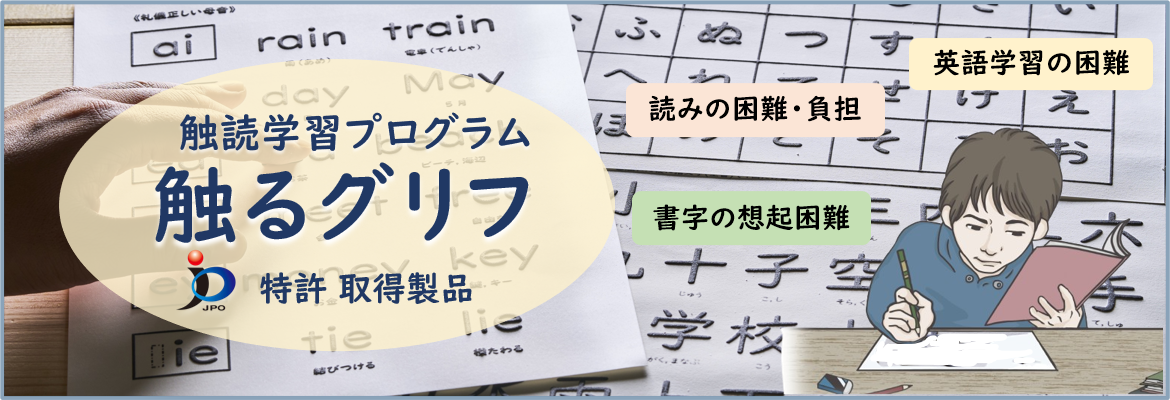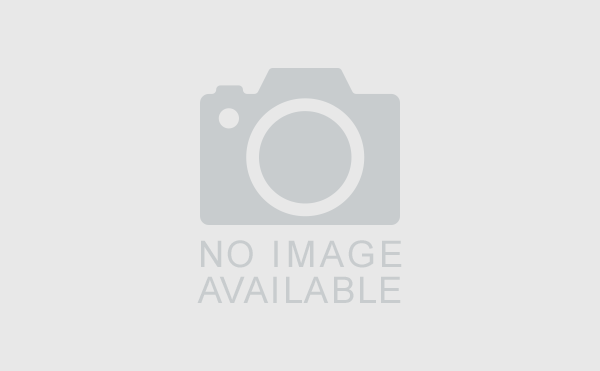保護者の方(体験談)
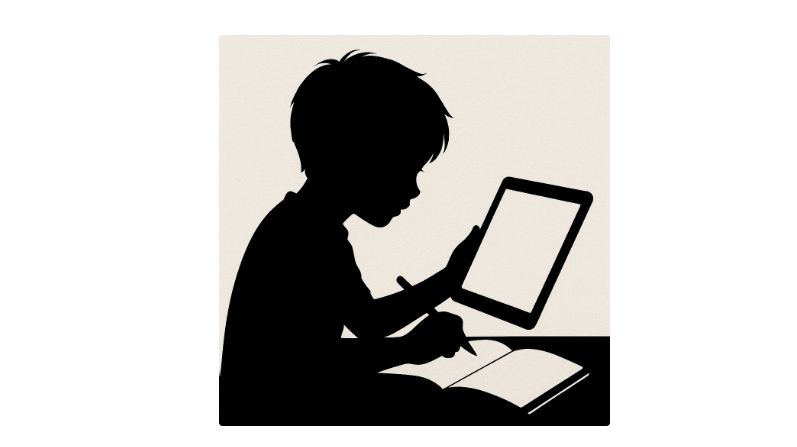
最初に子どもの様子に違和感を覚えたのは、小学校の低学年の頃でした。 学校生活を送るなかで、「落ち着きがない」、「文字を書く事を嫌がる」、「音読がうまくで きない」、「漢字がなかなか覚えられない」、「板書を書き写せない」などの様子が目立ち始 めました。
そこで、SNSや書物を調べたところ、子どもの様子が発達性ディスレクシア の症状と酷似していたことから、いろいろな医療機関をあたりました。
最終的には、学習障害の専門医が在籍するクリニックで検査したところ、「ADHD・発達性ディスレクシ ア」と診断されました。 子どもが小学生の時、学習面で最も困っていたことのひとつに、読み書きに対する心身へ の負担がありました。
具体的には、音読で大量の文字を読むと頭痛が生じる、漢字ドリル で何度も同じ漢字を繰り返し書くと疲労を感じるなどがあり、症状がひどい時は寝込むこ ともありました。
このため、小学校から「指示された学習を指示された期限に完了する」 ことができないことが多く、担任の先生からは「何なの。あの汚い字。」、「国語の授業で 皆と音読すると一人だけずれるのよね。困るわ。」と言われるなど、発達性ディスレクシア への理解不足による誤解と偏見に苦労しました。
そこで、診断書や発達性ディスレクシア に関する各種文献を小学校に伝え、障害者に対する合理的配慮を求めた結果、ひとまず 「板書は求めない。」、「漢字の課題は免除する。」など、書くことへの負担低減を受けるこ とができました。
また、国・自治体が主催する学力調査のテストでは、ルビ打ちや拡大コ ピーにより読みの負担を減らすとともに、ADHD の症状として集中力が保てないことがあることから、別室受験の配慮を受けることができました。
当初は配慮により学力が低下す ることを心配していましたが、学習能力には特に問題はありませんでした。一方、テスト の回答は筆記のままであったため時間を要し、試験時間の不足が問題でした。
子どもが中学校に入学し、改めて配慮を受ける必要がありましたが、中学校からは「合理的配慮を受けるには科学的根拠の提出が必要」と言われました。
そこで、専門医による最 新の診断書に加えて、宮崎言語療法室による音読検査の検査報告書を準備しました。
それ でも、中学校の先生方や市教育委員会に支援教育や学習障害に関する知識を有する人材が おらず、なかなか配慮が進みませんでしたので、市教育委員会の上位機関(県特別支援教 育センター)の学習障害に詳しい先生に間に入ってもらい、さらに医療機関の先生に授業 場面の観察をお願いして、子どもが授業で困っていることを中学校の先生方に説明しても らいました。
一方、小学校の時と比べて中学校では学習量が多くなったため、板書の書き取りや各教科 の課題の免除などこれまでの配慮だけでは本人の読み書きへの負担増加に対応できなくな りました。
そこで、全国で行われた合理的配慮の例として「試験時間の延長」、「ICT 機器 の使用」、「代読の導入」があることから、これらを合理的配慮として受けるべく学校と交 渉しましたが、ここでも発達性ディスレクシアへの理解不足による誤解と偏見に苦労しま した。(例えば、以下のようなことがありました。) ・支援会議にて中学校の先生方に要望を伝えたところ、校長から「最後まで解きたいか、 そこまでして点数をとりたいか。私たちは試験というもの知っている。
配慮を受けたい のであれば、クラス全員の前で自分の口から『障害を持っているから別室でテストを受 けるので認めて下さい』と言いなさい。」と言われました。
子どもは毅然と「それでも 受験したいです。また、周囲に自分の障害を話すのは絶対に嫌です。」と言い返しました が、子どもの学習意欲を否定するだけでなく、障害をカミングアウトさせようとする人 が平然と教育機関の責任者になっている現実を目の当たりにしました。
合理的配慮として「別室受験」と「時間延長」を試行した際、監視役の先生から「まだ か、まだか。」、「テストは読み書の速さをみるものだ。」と、子どもを急かす発言と態度 が繰り返し行われたため、自宅に子ども避難させて在宅でテストを受けました。
先生方 には、合理的配慮を実施する側としての負担に対する不満を抱えているようで、時にこ のような怒りを子どもにぶつけることがありました。
読みの負担低減として ICT 機器の読み上げ機能を利用しましたが、機械の読み飛ばしや 聞き取りにくい問題が生じました。そこで、人が読み上げた方が聞きやすいことから 「代読」を取り入れることを要望しましたが、学校側は「適切な人材がいない」ことを 理由に拒み続けたため、保護者が対価を支払う形で代読者を手配しました。
子どもが高校に入学し、改めて配慮を受ける必要がありましたが、中学校と同様に高校側 からも「合理的配慮を受けるには科学的根拠の提出が必要」と言われました。しかし、診 断書や主治医の意見書を提出しても、最初のテストで受けた配慮は中学入学時と同様の 「別室受験」、「拡大コピー」のみで、筆記による回答はそのまま残されています。
このよ うに、子どものライフステージが上がる都度、合理的配慮の交渉を初めからやり直す必要 があることに苦労しています。 高校はさらに学習量が増える一方、発達性ディスレクシアは語学、特に英語に苦労するよ うです。
一方、子供が通っている高校では、英単語のテストが頻繁に実施されますので、 宮崎言語療法室が開発した「触るグリフ」を活用して、英単語を学習しています。子ども は「使用する前は単語を思いだすのに時間がかかったけど、このツールを使用したらすっ と思い浮かぶ」と、効果を実感しているようです。
最後に、発達性ディスレクシアの子どもを持つ親からお伝えします。 発達性ディスレクシアのこどもが、小学校から中学校まで挫折せず、高校進学までこぎつ けた努力は、並大抵のものではありません。
しかし、高校進学で終わりではなく、子ども が立派に自立できることがゴールなので、それまではできるだけの支援をするつもりで す。
一方で社会に目を向けますと、音声自動変換入力など社会の IT 環境の進化には凄まじい ものがあり、鉛筆やペンで文字を書く機会がどんどん減っていることを感じています。将来、AI の進化とも相まって、読み書きなど発達性ディスレクシアの子どもの障壁となった ものが無くなる未来が来るといいですね。